
とりとめない象徴の綾
黒沢清の映画では、ドラマチックな大団円に向かってストーリーが結束し、登場人物の心情が加速するような事態は起きない。象徴的な出来事は起こるが、すぐさま日常のなかに溶け込んでいく。状況は小さな驚きを巻き起こしはするが、ゆるやかに現状復帰する。
異相の露呈と現状復帰はランダムに発生するが、わかりやすい起承転結が紡がれることはない。そのリズム感が、黒沢映画の基調だ。
「アカルイミライ」もそんなペースで進行する。笹野高史と浅野忠信は、終盤のクライマックスではなく、物語中盤で死ぬ。浅野の死は、父(藤竜也)や同僚(オダギリジョー)の人生にある程度影響を及ぼしはするが、その影響の余韻を残して映画を終えるようなことにはならない。
ラストシーンに藤とオダギリは登場しない。チェゲバラのTシャツを着た少年たちが、表参道をただダラダラと歩くだけで映画は終わってしまう。彼等のように特に苦悩するでもなく、平凡で怠惰な若者が「アカルイミライ」を築くのが世の常だ、とでも示唆しているのだろうか。
圧倒的な無意識を体現する浅野忠信
浅野忠信は、笹野高史が経営する工場で働いている。後輩がオダギリジョーだ。仕事ぶりや、オダギリと話している様子をみるに、おそらく浅野は何も考えてない。後輩のオダギリを可愛がっているようでもあるが、少なくとも情緒的な感情は全く見えない。
日本人の悪口を言う日本人は、この「情緒」を嫌悪している。それほど日本にはいまだに「情緒」がはびこってる。日本の気候風土や伝統を愛する右派的情緒も、グローバリズムを偏愛し、日本的伝統を軽蔑する左派的情緒も同調圧力が高く、逃れにくい。オダギリも藤も、無意識かつ無防備に、情緒に絡めとられている。
浅野が何故クラゲを飼っているのか? 「待て」と「行け」の指示のポーズの意味は? 多分なにもない。あるのは、浅野が内部に抱える怖ろしく深い闇だけだ。闇と虚無には情緒の入り込む隙はない。
不器用な青年像を演じるオダギリジョー
浅野と気が合い、自宅を訪れたりもしているオダギリは、不器用な青年だ。妹の彼氏との挿話によって誇張的に強調されているとおり、社会へ巧く適合できていない。
社会的にはまだ未熟だが、ファッションや音楽のセンスには優れていて、男性としての魅力は秘めている青年。この種の人物は、後天的に社会性を身に着け、結果的にバランス感覚を備えた中年になる場合が多い。俳優としてのオダギリがまさにそうで、30歳台には大いに魅力を発していたが、40歳を超えて少しバランシングしすぎて、少し魅力を失いつつあるようにも思える。
主体性のない笹野高史
笹野も何も考えていない人物だが、浅野のようなタイプとは全く違う。70年代初頭の空気、スポーツ観戦のノリ、最近の若い奴が聞いている音楽。そのときどきのマジョリティを抵抗なく、浅く受け入れる。主体性がないのだ。あるのは周囲との関係性と距離感のみ。人間関係など、巧くやっていくフリをすればいいと思っている。自分の考えなどという青臭いものは持つ必要を感じていない。
恐らく日本人の80%はこのタイプだ。協調性を重要視する農村のメンタリティをそのまま受け継いでいて、抽象的思考など、無意味だと思っている。仕事を質実にこなし、「くうねるあそぶ」を適当に楽しむのが身の程を知る人生なのだ。
こういう実務的な人物が、日本の折衷文化を下支えしてきたのだろう。彼等が無節操な多様性を持っているからこそ、浅野のようなエキセントリックな人物の新奇な意匠を受け入れたり、オダギリのような未熟な若者もじっくり育てたりできたのだ。
主体性を持て余す藤竜也
藤竜也は、日活後期にデビューしたベテラン俳優で、日本映画全盛期の活力を知っている最後の世代だ。やさぐれた70年代を走り抜け、80年代の甘い果実をたっぷり啜ってきた。渋いルックスは、男性に憧れられ、女性にモテてきた。
その姿は、「江戸の男」だ。関西人のような商才があるわけでもなく、農地に土着した農民でもなく、しがない毎日を送っている浪人。実務に長けていない藤のような人物は、ふらふらと放浪しつつも、実は無駄に頭が良く、自らの主体性の喪失に悩んだりもしている。
戦後の黄金時代を通して、男として勝ち続けてきたが、特に戦略的に振舞ってきたわけではない。時代ごとに意匠の違う虚飾を纏って懊悩していた姿が、周囲には魅力的に映ってきただけだ。
「アカルイミライ」の藤は、息子を理解することができなかったことを悔い、オダギリとの間に、改めて父親の責任を再構築しようとする。しかし、オダギリには藤とは別の懊悩があり、超えるべき父性のハードルが必要な年齢でもない。クールに懊悩してきたあの藤竜也が、こんなお節介な老人になるなんて。昭和の底の浅さを嘲笑う黒沢の笑みが見え隠れする。
変わらない世界
昭和を代表するような藤と笹野の半生。オダギリも、オーソドックスな若者の典型であり、昭和に多かったタイプだ。彼等は特に秀でるところもない、どこにでもいる無個性な男であり、典型的な類型に容易に分類できる。実は平成も令和も、昭和とそんなに変わらない。新人類など全く登場していない。時代の位相が表面的に移ろっているだけで、人間の性格などそうは変わっていないのだ。
おそらく黒沢は、そのことに苛立っているのではないか。新しい時代には、新しい意識を持った人々が次々と登場し、革新的に世界は進化していく、ということをごく若い頃、信じた時期があったのではないか。
戦後世界は、そう黒沢に誤解させるほど、文化や経済を目まぐるしく動かした。黒沢だけでなく、誰もが「アカルイミライ」を信じていた。21世紀には、宇宙に植民地を持ち、優秀な頭脳を持ったロボットに労働を任せるようになる筈だ。
ところが、そんなことには全然ならなかった。そして、これからもそんな風には絶対にならないことが明らかになった。おそらく人類文明は1980年代にピークを迎えたのだ。全面核戦争が避けられたのは奇禍だったが、一瞬の破滅を潜り抜けた後は、緩やかな退行が待っているだけだったのだ。
興隆期に整えられたインフラや社会制度は、人々の生活に強固な安定をもたらしている。しかし、安定しているからこそ、破壊による新たな活力の創出も起こらない。21世紀は「アフターワールド=死後の世界」だったのだ。核戦争や宇宙人の侵略が起こり、一気に滅亡したほうが、ドラマティックだった。SF映画的な起承転結なら、そうあるべきだった。しかし、そうはならなかった。そうならなかった場合のパラレルワールドに、活力など起こる筈がない。
悪い冗談のような世界が我々の眼前に存在しているのだが、別に不快だったり苦しかったりすることはない。むしろ20世紀よりも快適な生活を送っている。それゆえか、藤も笹野もオダギリも、悪い冗談に気づいていない。家族や人間関係や経済やファッションにまだ依存している。しかし、そんな20世紀的な人間の意匠は、摩耗し始めている。意味を喪失しつつあるのだ。極めてゆっくりではあるが、創生の大いなる虚無に回帰し始めているのだろう。
こんな「アカルイミライ」を、無意識のモンスターである浅野は、滅ぼそうとでもしたのか? あるいはクラゲに何らかの再生を託したのか?
さっぱりわからない。









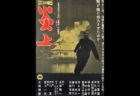






LEAVE A REPLY